 |
#18 |
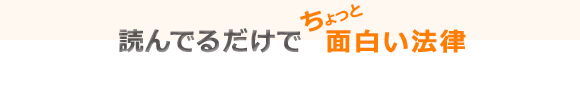 |
時には裁判所の話を |
|
たまには弁護士らしく、裁判所のお話でも。 某T京地方裁判所では、数年前、裁判所の敷地のすぐ外の歩道に、判決や裁判官の訴訟指揮に対するクレームをでかでかと記載した看板が乱立していたことがありました。前を通るたびに「この件で一体何があったんだろう」と淡い興味をかき立てられていたものですが、なぜか最近は見かけません。 そんな中でも記憶に残っているのが、次の経緯をたどった看板合戦です。 1. 裁判所のフェンスの外側(歩道側)に、裁判所へのクレームを記載した看板が設置される。 2. 1の看板の近くのフェンスに、裁判所が「歩道にはみ出して看板を設置しないでください」という注意書きの看板をくくりつける。 3. 2の注意書きの横に、(恐らく)1の看板の設置者が、「裁判所の植木だって歩道にはみ出してるだろうが」という反論の看板を更に設置する(確かに枝葉がちょろっとフェンスから歩道にはみ出している)。 4 いつの間にか1~3が全部撤去される。 3を見たときは「その発想はなかった」と笑いをこらえきれませんでしたが、欲を言えば、裁判所の本気の再反論を見たかったところです。 なお、裁判所の敷地内での振舞いについては、基本的に裁判官やスタッフの指示に従うことが求められており、よっぽどのことがなければ大人しくしておいた方が無難です。これは、裁判官には法廷の秩序を維持する権限が、庁舎等の管理者には管理権があるためです。 筆者は一度だけ、この法廷の秩序維持のための命令を受けた経験があります。 あれは寒い冬の日でしたが、法廷の中は税金による暖房でここちよく暖まっていました。例によって傍聴席には誰もおらずガラ空きであったため、筆者は、中国人民解放軍の放出品のようなくたびれたコートを傍聴席の隅に置いたまま、法廷のバー内の代理人席に座りました。 すると、開廷後、裁判官がおもむろに「あのコートは代理人のものでしょうか。それなら手元に置いてもらえると…ね?」とマイルドな命令を発しました。意訳すると、「傍聴席はお前の荷物置き場ではないし、置き引きでもされたら色々面倒だからしまっとけ」ということかと思います。 「あなたの目の前で現行犯でかっぱらうチャレンジャーがいるとでもお思いか?ここはフードコートではないし、たとえフードコートでもあんなボロいコートは誰も盗まない」 という反論が反射的に脳裏に浮かびましたが、ここで意味なく怒らせて退廷命令でも受けようものなら生ける伝説になってしまいます。小心者の筆者は、元気よく「はい!」と返事をし、光の速さでそそくさと回収に走りました。 法曹界のすみっこにひっそり棲息する者として、秩序は大切にしたいものです。 |
安心した事業承継に繋がる |
 |
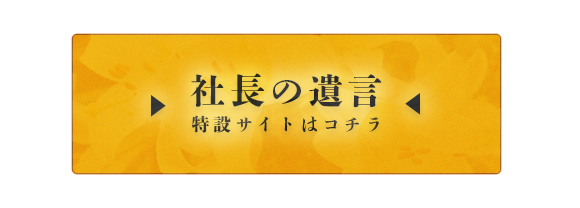 |
会社経営と株式 |
|
今回は具体的な株式譲渡についてお話をしていきます。 前回お話しした通り、株式の交付の要否はありますが、当事者間では株式の譲渡はお互いが合意すれば有効におこなうことができます。 ところが、会社との関係ではそれだけでは終了というわけにはいかないのです。 というのも、繰り返しになりますが、株式の譲渡は原則合意のみでできる、つまり、非常に簡単にできるため、いつどこで株式の譲渡があったのかを全て会社が把握しておくことは困難です。 そのため、会社からすると、株主が誰であるかを確認する方法が必要となります。それは、単に株券を持っている、というだけでは確実ではありません。株券が盗まれたものである可能性も否定できないためです。そこで、会社法は、会社が株主であることを確認するのは株主名簿の記載にしたがって判断すれば足りる、ということにしました。つまり、株主名簿に記載されている人が真の株主でなかったとしても、会社は株主名簿に株主と記載された人に、例えば、株主総会の通知を発送するとか、株式の配当を行っても、責任を問われないとういことになります。逆に言えば、株式譲渡を受けた人からすると、自分が株主であることを会社に認めてもらうためには、株式を譲り渡した者と共同して株主名簿の名義書換請求をして株主として名義書換してもらう必要があるということになります。 したがって、株主側としては、株式を譲り受ける旨の合意をしただけでは、株主の権利を会社に主張したり行使したりできるわけではないということは覚えておいてください。 なお、名義書換請求の方法については、会社法では特に規定していないので、口頭で行うこともできます。但し、実務上は証拠として残しておくために、内容証明郵便よる請求を行って残しておくことがベストですし、そこまでは大変だということであれば、せめて、書面をメールやFAXで取り交わす等の方法で行っておくといいでしょう。 また、株式の譲渡は口約束だけでも簡単にできることから、株主が二重三重に株式を譲渡することもあります。このような場合にも、株主は誰かを決定する判断材料となるのは株主名簿です。この点でも株主名簿の書換が非常に重要であることがご理解いただけたと思います。 次回はこれまでお話ししてきた株式譲渡が制限される場合についてお話しします。 ●「事業承継」の流れや課題ついてコラムはコチラ●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから ●もっと詳しく「会社支配権紛争」のページはコチラから |
顧問弁護士をお探しなら企業法務に強い高瀬総合法律事務所へお任せ下さい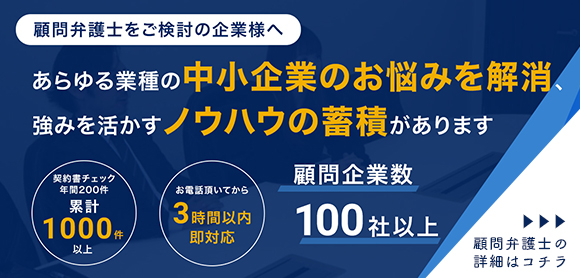 |
|