
「介護してきたのは私だけ」 相続人どうしで扶養をめぐる調停に。どうする?
2025年7月29日
親が亡くなり、相続が始まる。
それは同時に、家族の「積もり積もった感情」が表に出てくる瞬間でもあります。
「介護をしてきたのは私だけなのに、他の兄弟は何もしなかった」
「母の介護について、扶養請求の家事調停申立書が裁判所から届いた」
「遺産分割には応じるつもりだったけど、生活が厳しいから少し援助してほしい」
そうした感情がこじれ、相続人どうしで扶養をめぐる家庭裁判所の調停に発展するケースも少なくありません。
このコラムでは、実際に多い「相続と扶養請求のトラブル」について、弁護士の視点から背景と対応を解説します。
事例:親の介護をしてきた長女に、弟からの“扶養請求”が届いた
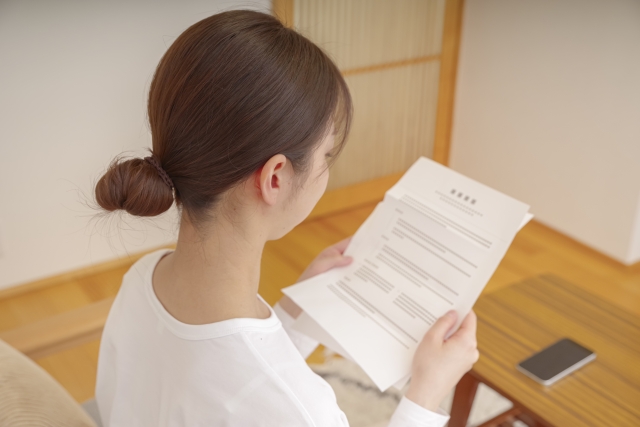
長年実家で両親と暮らし、親の介護を一手に引き受けてきた長女Aさん。
父の死後、母を在宅で看取ったのち、両親が遺したわずかな財産を兄弟3人で分けることに。
ところが遺産分割協議の途中、弟から「生活が苦しいから扶養してほしい」との調停申立書が家庭裁判所から届く。
「介護の負担は一切してこなかったのに、今さら扶養義務?」「そもそも、私も余裕なんてない」
Aさんの戸惑いと怒りは、相続をめぐる感情のこじれが、ついに法的なステージに移った瞬間でした。
「扶養義務」と「相続」。法的にはどう考えられるのか?

扶養義務は相続とは別のもの
民法第877条では、親族間には生活保持義務(生活を維持するための援助)があるとされています。
つまり、たとえ相続でもめていたとしても、兄弟姉妹間での扶養請求が成立する可能性はあります。
ただし、兄弟姉妹間の扶養義務は「生活扶助義務」と呼ばれ、親子間などより義務の程度は軽いとされています。
本人の生活に余裕がない場合は、拒否できることもあります。
感情的な問題が調停のかたちで表れることもあります。

このようなケースでは、扶養請求そのものというより、
- ・「親の面倒を私が見てきた」
- ・「兄弟なのに無責任だった」
- ・「本当は遺産をもっと取りたいけど言いづらい」
といった相続や介護にまつわる不満や葛藤が、扶養という法的手段に形を変えて表れることが多いのが現実です。
そのため、単に法律だけで白黒をつけようとすると、かえって関係が悪化することも。
「弁護士に相談してもいいのかな?」と思っている方へ

このような複雑な場面では、法律的な見解と感情的なバランスの両方に配慮した対応が必要です。
弁護士は以下のようなことができます。
- ・扶養義務の有無や範囲について、法的に冷静に検討
- ・ご本人の収支や健康状態から「支払えるかどうか」の現実的判断
- ・遺産分割や過去の介護負担との関連を踏まえた交渉戦略
- ・調停対応のアドバイス・同席・書面作成などの実務支援
特に、「話し合いの場で自分の立場をうまく説明できるか不安」という方には、調停に同行することも可能です。
家族のもめごとは、感情だけでなく、法的な整理も必要になることがあります。
扶養請求の調停は、単なる金銭請求ではなく、家族関係のこじれが表に出る場でもあります。
だからこそ、感情的になりすぎず、第三者の視点で状況を整理することがとても重要です。
「これって払わなきゃいけないの?」「納得いかないけど、どう対応すべき?」
そんなときは、どうか一人で抱え込まず、弁護士に早めにご相談ください。
📞 初回相談無料・オンライン相談可
- ・扶養調停の通知が届いて不安
- ・相続でもめていて気持ちが整理できない
- ・法律的にどう考えればいいか知りたい
お気軽にご相談ください。ご本人の気持ちと状況に寄り添いながら、一緒に対応策を考えます。



