
家族信託と後見人制度の違いとは?認知症対策として弁護士が解説
2025年10月16日
認知症と財産管理の課題
高齢化社会が進む中、認知症による財産管理の問題は多くのご家庭で直面する課題です。認知症が進行すると、預金の引き出しや不動産の売却といった法律行為ができなくなります。
その結果、介護費用の確保や資産の有効活用が難しくなるケースが増えています。こうした問題を解決するための仕組みが「家族信託」と「後見人制度」です。
家族信託とは?
家族信託(民事信託) とは、財産の管理や承継を信頼できる家族に託す仕組みです。委託者(親)が受託者(子)に財産の管理を任せ、契約で定めた目的に従って柔軟に活用できます。
例えば、親が認知症になった後でも、受託者である子が不動産を売却して介護費用に充てることが可能です。
家族信託が優れている点(メリット)

- 柔軟性が高い
契約設計次第で「将来不動産を売って介護費用に充てる」「相続の分配を指定する」といった自由な運用が可能。 - 認知症発症後もスムーズに資産活用できる
不動産売却や投資など、裁判所の許可が不要。 - 相続対策も兼ねられる
認知症対策と遺産分割対策を同時に進められる。
この点は後見制度に比べて圧倒的に強みです。
ただし家族信託にも弱点がある(デメリット)

- 契約できるのは「元気なうち」だけ
すでに認知症が進んでいる方は利用できません。 - 医療・介護に関する代理権は限定的
財産管理はできても、入院契約・介護施設との契約などは信託契約の範囲外になることが多い。 - 受託者リスク
任せる家族の不正や紛争のリスクがあり、トラブル防止のため専門家の関与が望ましい。
後見人制度とは?
成年後見制度 は、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や法律行為を行う制度です。本人の判断能力が低下してから利用できます。
後見制度が優れているケース

- すでに認知症が進行している方
家族信託は使えないので後見制度一択。 - 家庭裁判所の監督が必要な場面
例えば、本人が詐欺に巻き込まれる可能性があるなど、権利保護を重視したいケース。 - 家族間の信頼関係が弱い場合
親族間で受託者を決めるのが難しい場合には、第三者後見人が有効。
一方の後見制度のデメリット

- ✅財産の処分や活用は裁判所の許可が必要で、柔軟性に欠ける。
- ✅毎年、後見人報酬が発生する。
▼TIPS▼ 後見人報酬について
成年後見制度では、後見人の報酬は原則として本人(=被後見人)の財産から、後見人へ毎年報酬が支払われる仕組みになっています。
- ✅報酬額は家庭裁判所が本人の財産状況や業務内容を踏まえて決定
- ✅一般的には 月2万円〜6万円程度 が目安(年間24万〜72万円ほど)
- ✅不動産の売却や多額の財産管理がある場合は報酬が上乗せされることも
つまり、後見制度は「継続的なコスト」がかかる点を理解しておく必要があります。
家族信託と後見人制度の違い(弁護士が解説)
| 項目 | 家族信託 | 後見人制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 本人が元気なうちに契約可能 | 認知症発症後に家庭裁判所へ申立てして利用開始 |
| 柔軟性 | 契約次第で幅広い財産活用が可能(不動産売却・資産承継など) | 裁判所の監督下で制限あり。財産処分は許可が必要 |
| 費用感 | ・公証役場費用(収入印紙や手数料)合計で数万円〜10万円程度 が一般的。 ・専門家(弁護士・司法書士)の報酬が契約時に発生 | 家庭裁判所への申立費用は数万円程度。ただし後見人報酬(年数十万円程度)が継続的に発生 |
| 監督・信頼性 | 受託者(家族等)が中心であることがほとんど。契約次第では弁護士や司法書士が受託者・監督人に入るケースもある | 家庭裁判所の監督下で後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任される |
こんな時は弁護士への相談が安心です
家族信託や成年後見制度は、司法書士が登記や手続きに強い一方で、紛争性や法律的な判断が絡む場面 では弁護士に相談するのが適しています。特に以下のような場合は、弁護士への相談が望ましいでしょう。

家族間で意見が対立している場合
「長男に任せたい」「全員で平等に管理すべきだ」といった意見が分かれているケースでは、感情的な争いに発展しやすいため、法律の専門家である弁護士が間に入ることで冷静な調整が可能です。
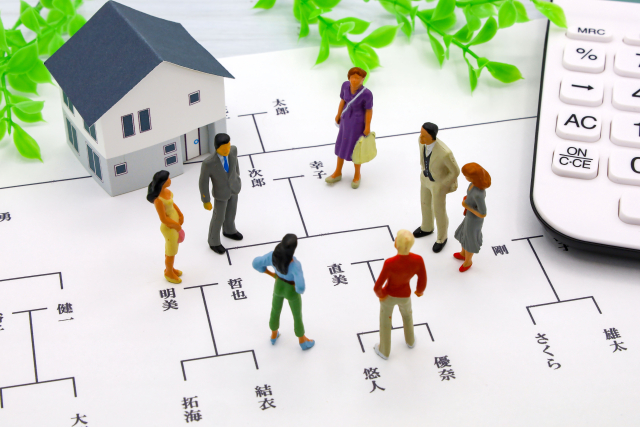
相続争いにつながる可能性がある場合
信託契約に遺産分割をどう組み込むかは慎重な設計が必要です。将来、兄弟姉妹の間で争いになることを防ぐには、紛争解決まで見据えた弁護士の関与が欠かせません。

財産規模が大きい・複雑な場合
不動産が複数あったり、会社経営や事業承継が絡むケースでは、法律・税務・経営の知識を総合的に扱う弁護士の強みが活きます。

契約が無効になるリスクを避けたい場合
家族信託は設計次第で「せっかく契約したのに法律的に効力が認められない」という事態も起こり得ます。法的リスクを事前に潰すためには、契約書作成の段階から弁護士に相談するのが安心です。
「家族や財産の状況がシンプルで登記中心なら司法書士、紛争やリスクを含む複雑なケースは弁護士」 という整理になります。
まとめ
認知症対策や財産管理は「あとで考えればいい」と先送りできる問題ではありません。
家族信託と後見制度、どちらが適しているかを迷ったら、専門家に相談するのが一番の近道です。
弁護士がトラブルを未然に防ぎ、安心できる準備をサポートします。
相続や家事事件に精通する弁護士にまずはご相談下さい。



