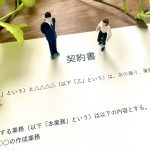契約書を作成する必要はある?契約書を作成する時の注意点とは?
2022年12月21日
ビジネスの場では日々様々な契約が交わされています。 契約は企業同士の取引など、約束事や条件などの取り決めを合意するために用いられますが、一部の類型を除く契約のほとんどは、契約書の作成が法律で定められていないため、契約書が作成されずに口約束だけで取引がなされる場合も少なくありません。 本記事では、トラブルの実例を交え、契約書の必要性と作成時に気をつけなければならないポイントを解説します。
契約書はなぜ必要?
正式な契約書を交わさないまま取引がスタートする理由として、
「あの会社とは長年の付き合いだから揉めることはないだろう」
「大手企業との取引だからトラブルになることはないだろう」
「契約書を作るほど大きな取引じゃないから良いだろう」
「どのような内容で契約書を作ればよいのか分からず面倒くさい」
などといったようなケースが多いのではないでしょうか。
契約書を作成すると、相手企業を信用していないように感じられてしまうのではないか?と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、事前にしっかりと取り決めを書面にして合意することは、自社にとって武器となるだけでなく相手方から理不尽な請求をされるリスクを回避するための盾となるのです。お互いの信頼関係を保ち、健全な取引をするためには契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。裏を返すと相手側が契約書を作成し、自社がサインをする場合は後々揉めないよう、注意して確認する必要があるということになります。トラブルに陥った際に自社が不利になってしまう記載はないか等、様々な状況を想定し、取り決めに関する記載漏れがないかどうかしっかりと確認しなければサインをしてはいけません。相手方から提示された契約書の内容をよく読まず、安易に合意のサインをしてしまうことはリスクにつながると同時に、取引先から「契約リスクを全く考えない企業」として軽く見られてしまう可能性もあるので注意しましょう。
契約書を自分で作っても大丈夫?
今は知りたい情報のほとんどをインターネットで見つけられる時代。もちろん契約書についての情報や、テンプレートなどもインターネットで検索すればたくさん見つけることができます。しかし、契約書作成時に気をつけなければならないのは、「実際の取引実態に即しているかどうか?」です。インターネットで見つかる契約書のテンプレートは、あくまで「テンプレート」ですから、一般的に広く様々な業種の方に適用するよう作られています。そうすると個々の契約にはどうしても漏れが出てしまい、リスクやトラブルを回避するためにせっかく作成した契約書が意味を成さないというケースも多々あるのです。テンプレートを使用せず自分で作成する場合であっても、様々な状況を想定し、抜けのない完璧な契約書を作ることは専門的な知識がないと難しいでしょう。
ここで、取引の際に契約書は作成したものの、記載が曖昧だったためにトラブルで明暗が分かれてしまった事例をひとつご紹介します。
実際のトラブルに見る、契約書作成時の注意点
これは電子機器メーカーA社と測定機器メーカーB社が、液晶パネルの欠陥検査を自動で行う装置を共同で開発するという内容の『共同開発契約』を交わしたものの、後に問題となった事例です。 本契約はB社が装置を開発し、A社は開発した装置を顧客に販売することを予定して交わされました。 ところがB社は一定の精度を有する成果物を納期までに納品することができなかったため、A社がB社に対し損害賠償請求を行いました。
裁判では、一審(地方裁判所)はB社に対して装置を完成させて納品する義務があったとしてA社の請求を認めたものの、二審(高等裁判所)ではB社は信義誠実の原則に基づき通常の開発製造行為をする義務はあるがそれに尽きる。すなわち、完成させて納品する義務まではなかったとしてA社の請求が認められず、真逆の結論となってしまいました。これは一審と二審で共同開発契約書の解釈が全く異なったということになります。
ではなぜ一審と二審で共同開発契約書の解釈が分かれたのか。その最大の要因は、契約書にB社の役割が具体的かつ明確に記載されていなかった事です。 具体的に「B社は仕事を完成させる義務がある」ことや「請負型である」といった文言を明記しておけばA社の請求が認められた可能性は高かったでしょう。 逆にB社とすれば「B社は信義誠実の原則に基づき開発製造業務を遂行する義務のみを負う」と明記しておけば、今回のように納期までに完成して納品できなくとも、A社から訴えられる可能性は低かったでしょう。
以上のように、契約書に何をどのように書くかによってトラブル時の結果が全く異なる場合があることをご理解いただけたと思います。そして、ご紹介した事例でも分かる通り、自社の責任範囲についてどのように記載すればトラブルを回避できるのかは、法律の知識がないと難しい場面も多々あります。 慎重に進めたい大事なお取引の際には、私達のような法律のプロにご相談いただくと安心かもしれません。
本記事がご参考になれば幸いです。